近況報告
クラブ運営委員長 赤沼典昌君
こんにちは。今年度クラブ運営委員を担当いたします赤沼典昌(あかぬま のりあき)です。
どうぞよろしくお願いいたします。
高校の先輩、高木和久会員にお誘いいただき、信州友愛ロータリークラブに入会させていただきました。
入会当時の私は、ロータリークラブは時間に余裕のある経営者などが交流し、奉仕している団体、という程度の認識でした。
そのような中、例会等場で「職業奉仕」とのお話しを伺い、社会保険労務士として「障害年金の裁定請求」に取り組んでみたことついてお伝えしてみようと思います。
私はサラリーマン時代、約25年にわたり人事・労務に関する業務に従事してきました。2017年に独立してからは、人材紹介事業と並行して、企業の人事労務に関するコンサルティングや教育研修の企画・講師業を行ってきました。
2020年に社会保険労務士として登録した後も、従来の業務の延長として人事・労務関連のご依頼に限定してお受けし、社会保険関係の業務については基本的にお断りしておりました。
そんな中、人材紹介事業で、
40代で脳梗塞を発症し、手足に麻痺が残る方
子どもの頃から対人恐怖があり、20代で統合失調症と診断され、他人と一緒に働くことが困難な方というようなハンディキャップを抱える求職者と出会いました。
人材紹介事業は、企業様に求める要件を具えた人材をご紹介し、採用いただくことで報酬をいただくビジネスです。そのため、ハンディのある方々を企業に採用して抱くこと、就業を支援することは簡単ではないのが現実です。
しかし、ハンディキャップある人たちを「就業能力が低い」として支援の対象外とすることは、日々の生活に困窮する方々を見過ごすことになりかねません。
真に支援を必要としている人々を放置することへの葛藤から、私は「障害年金裁定請求」の支援に取り組むこととしました。
調べてみると、我が国には約1,000万人(人口の約9%)の障害者がいるとされ、そのうち障害年金を受給している方は約210万人(障害者の約22%)にとどまっています。
受給していない理由としては、
制度そのものを知らない
手続きが複雑で難しい
自分は対象外だと思い込んでいる
などが挙げられます。
社会保険労務士として、制度の周知や手続きの代行を通じて、障害をお持ちの方々の“Life” (くらし・人生・命)を支えることは、意義深い取り組みであると感じています。
・・・・・・・・・・・
【障害年金とは】
病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出るほどの障害が残った場合に支給される年金です。
対象となる障害の状態(等級)
1級:常に介助が必要な重度の障害(例:寝たきり、視力がほぼない)
2級:日常生活に介助が必要な障害(例:歩行困難、精神障害で外出が困難)
3級(厚生年金のみ):仕事に大きな制限がある障害(例:片腕が使えない)
※一時的な病気やケガでも、障害認定日に該当する状態であれば支給対象となる場合があります。たとえば、がんの手術後に身体機能が著しく低下したケースなども含まれます。
・・・・・・・・・・・
最近では、知的障害があり、子どもの頃は養護学校や特別支援学級で学び、大人になってからの就業が困難な若者数名の障害年金申請を支援させていただきました。
彼らは親御さんの支援に全面的に依存して生活しており、その支援が途絶えた場合、生活の維持が困難になることが懸念されていました。親御さんも将来への強い不安を抱えていましたが、障害年金の受給が決定したことで、「この子が一人になっても最低限の生活が保障される」という安心感を得られたとお話しくださいました。
また、障害年金の受給決定は、本人にとっても「社会から認められている」という実感につながり、自尊心の向上や生活意欲の回復にもつながる場面が見られました。制度の存在が、生活の安定だけでなく、精神的な支えにもなっていることを改めて実感しています。
このような経験を通じて、障害年金制度が果たす役割の大きさを痛感しています。今後も、制度の活用を必要とする方々に寄り添い、安心して暮らせる社会づくりに貢献していきたいと考えています。
もし皆さまの周りに、病気やケガでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ障害年金制度についてお知らせしてあげてください。一人でも多くの方が安心して暮らせる環境を手に入れられるよう、情報の共有と支援の輪を広げていただければ幸いです。
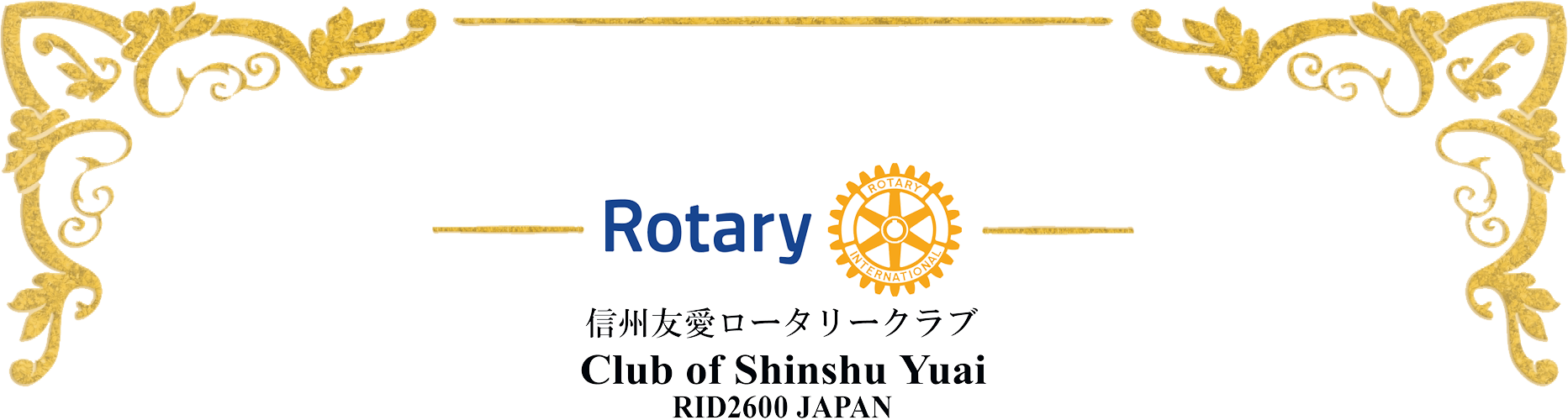

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
