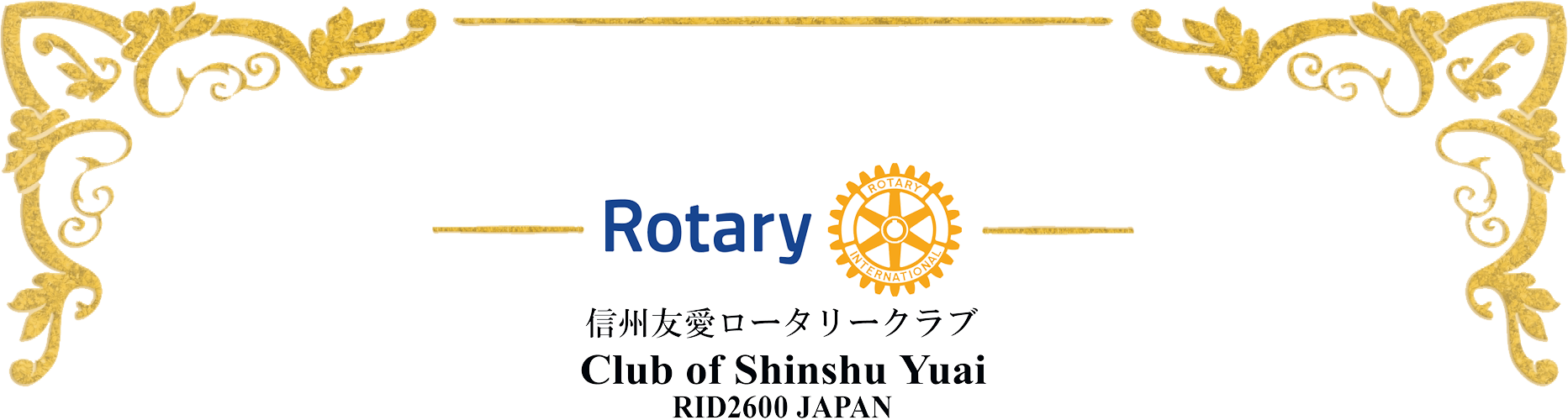
例会開催は、毎週水曜日0時より開催となっております。
 【会長挨拶】
【会長挨拶】
下記の皆様よりニコニコボックスを頂きました。
信州友愛RC 乾みゆ紀君
「IMでは有意義なお時間をいただきありがとうございました。」
信州友愛RC 新本登志也君
「よろしくお願いします。」
信州友愛RC 金児進君
「11月になりました。浅間山にも初冠雪。いよいよ冬シーズン到来です。会員の皆様におかれましては風邪などひかぬよう充分お気を付けください。
今月もよろしくお願いします。
」
長年、私は言葉にできない“生きづらさ”を感じてきました。何かがおかしい、何かが違う。
その感覚は何十年も心の奥にありましたが、近年になってようやく、その違和感の正体に気づき始めました。
それは、私たちが暮らす社会の“二つの当たり前”に対する疑問でした。 一つは資本主義という仕組み、もう一つはお金の仕組みです。
資本主義は、一部の金融資本家が富を得るために、誰も気づかないよう巧妙に設計された構造であり、私たちは疑問を持つことなく、当たり前のものとして受け入れてしまっています。
お金も同様です。もともとお金は、金との交換券として発行され、人と人との価値のやり取りを円滑にするための道具でした。ところが現代では、銀行が貸し出すことでお金が生み出される「信用創造」の仕組みが主流
となっています。つまり、借金によってお金が生まれ、そこには必ず利子が付きます。そしてその利子は、金融資本の利益となっていきます。
この構造では、経済が常に成長し続けなければならず、預金も借金によって作られるため、私たちは返済のために働き続ける“経済的な奴隷”のような状態に置かれます。その中で、限られたお金を奪い合い競い合う。誰かの利益が他の誰かの損失になる。そんなゼロサムゲームが繰り広げられています。
利子の存在によって穴埋めができず、借金は雪だるま式に増えていき、アメリカでは天文学的な負債で返済不能なレベルに達しています。もう資本主義そのものが限界に近づいていると感じています。
さらに、経済成長を前提とした社会は、有限な資源の消費を加速させています。必要以上に浪費し、感謝もなく使い捨てる そんな浪費社会の現実に、私は深い疑問を抱いています。
確かに、現代は豊かで便利な世の中になったとは思います。けれど、これが本当の豊かさであり、幸せの形だとは、私には思えません。 物質的な充足があっても、心が満たされていない。情報が溢れていても、真実が見えにくい。そんな今だからこそ、私たちは“本当の豊かさ”とは何かを問い直す必要があるのではないでしょうか
。
お金の仕組みそのものが、資本主義の拡大を支える装置となり、私たちの暮らしや価値観をも変えてしまったのです。そして、それが真実かどうかを疑うことすら許されない“利権のための常識”もあります。化石燃料、地球温暖化、ワクチンなどなど、さまざまな分野において、私たちは真実かも分からない情報に翻弄され、疑うことを忘れてしまっているように感じます。
本来、人間は自然と寄り添い、循環の中で生きる存在だったはずです。縄文時代のように、自然と共にあり、分かち合い、感謝しながら暮らす――そんな生き方が、人間の本質に近いのではないかと思うのです。
この気づきは、私にとって大きな転換点でした。今では、自然との共生、感謝、愛といった価値を大切にしながら、自給自足もふまえて、子どもたちの未来のために循環する生き方を模索しています。
経済の仕組みをすぐに変えることは難しいかもしれません。けれど、私たち一人ひとりが“違和感”を言葉にし、“感謝と循環”を選び直すことで、未来は変わると信じています。
ロータリークラブの皆さまは、地域社会や人とのつながりを大切にされている方々です。だからこそ、こうした問いを共有させていただきたいと思いました。私たちが今、何を大切にし、どんな価値観で生きていくのかそれが、次の世代への贈り物になると感じています。
私はこれからも、自分の感覚を信じ、自然と人とのつながりを大切にする生き方を探求していきます。
ありがとうございました。


